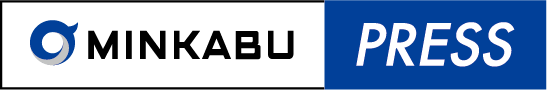【独占取材】平将明衆院議員(デジタル大臣)「サイバー防御は成長分野」、AI時代の日本再興シナリオを聞く
─トランプ米政権に「ディープシーク」、ゲームチェンジに日本はどう向き合うか─
日経平均株価が過去最高値をつけた2024年も今は昔。米半導体のエヌビディア<NVDA>にマネーが集中した「AIバブル」は鳴りを潜め、米ハイテク株が調整色を濃くするなかで日本株に下押し圧力が高まっている。それでも日本国内ではデータセンターの建設ラッシュの様相を呈し、企業がAIの活用により生産性を向上させようとする取り組みは不可逆的なものとなっている。
失われた30年を経て日本経済が再興・成長するうえで、AIやブロックチェーン 技術はどのような役割を担うこととなるのか。AI規制に消極的でかつ、暗号資産業界の成長に舵を切るトランプ米政権の誕生はどのような変化をもたらすのか。自民党でAIの進化と実装やWeb3に関するプロジェクトチームを立ち上げ、関連政策の提言・立案に長年携わってきた平将明衆議院議員に、今後の方向性やビジョンについて話を聞いた。
●一貫した方針
──米テック企業が日本国内でのデータセンターの巨額投資に踏み切りました。
「AIが日本経済を成長させる重要なテクノロジーであることは間違いない。先般出席したダボス会議ではトランプ大統領の政策とともに、AIに関する話題で持ち切りとなった。生成AI に関して日本は害のある部分は既存の法律で対応しつつ、そうでない部分はアジャイルに対応し、過剰な規制や、包括的な規制は掛けないという方針でここまで来た。『世界一AIフレンドリーな国を目指す』という一貫したスタンスを堅持したからこそ、日本国内において米巨大テック企業によるAIデータセンターの巨額投資が実現した。日本は地政学的な観点でも、安心して投資をできる国だ。日本への投資の流れは今後も続いていくだろう」
──AIを活用した新たなサービスの誕生も後を絶ちません。
「バックオフィス業務を効率化するうえでAIは劇的なインパクトをもたらす。霞が関での業務も同じだ。デジタル庁と警察庁が闇バイトの防止に向け、怪しげなX(旧ツイッター)の投稿の抽出業務にAIを導入した事例では、警察庁の業務量をデジタル庁の試算で8割削減することができた。デジタル庁ではパブリックなトークルームでのやり取りをAIで取り込み、業務上のFAQ(よくある質問)を作成するといった取り組みも進めている。デジタル庁が安全性を確認しながらAIを業務に導入し、それを横展開することで、政府のAI実装は一段と加速していくこととなる。民間においても今後、日本の社会課題の解決につながるAIサービスが一気に広がる可能性が高い。ロボティクスとAIを掛け合わせたサービスも始まるだろう。日本はロボティクスで強みを持つだけに、ここでどのような絵が描けるか、成長戦略という観点からもポイントとなっていく」
──トランプ政権の誕生はAIやブロックチェーン、インターネット上の情報を分散管理するWeb3の領域において、新たなゲームチェンジをもたらしそうです。
「日米連携の強化という点でもプラスだ。そもそも最先端のAIは、安全保障と切り離すことができない。ファイブ・アイズ(米英など英語圏5ヵ国)からみて、セカンド・レイヤーとなる日本やドイツなどが最先端のAI半導体の供給を受けるには、強固なサイバーセキュリティー体制の構築が不可欠となる。(能動的サイバー防御を可能にする)サイバー対処能力強化法案は、グローバルスタンダードのセキュリティー体制を実現するものだ」
「AIとブロックチェーンは互いに作用を及ぼしあうものであって、相互作用によりそれぞれの進化が加速するという関係性があると私は考えている。日本においても、円建てのステーブルコインの早期実用化を目指す必要がある。円建てステーブルコインの導入によりWeb3の実装例を国内で更に生み出すことが可能となり、それらをグローバルに展開できるようになる」
●「ディープシーク」がもたらす変化
──中国製の生成AI「ディープシーク」が波紋を広げています。株式市場ではエヌビディアの成長に対する楽観的な見方が薄れるようになりました。
「ディープシークに蓄積される情報は、中国国内でのサーバーにデータが保存され、データの扱いについては中国の法律が適用される。日本のように個人情報が守られる確約はない。このような情報を個人情報保護委員会が国民に向けて発信した。またNISC(内閣サイバーセキュリティセンター)を通じて、政府での生成AIの業務利用に関する留意点について改めて徹底するように求めた。米国の力をそこまで借りずに、こうした生成AIを誕生させたという点については衝撃的でもあり、中国の開発人材の厚みを感じさせる」
──日本にとっての同盟国・同志国との連携も一段と重要になっていきそうです。
「AI自体、安全保障上の制約を常に受けるものだ。経済安全保障の文脈を考えれば、組める相手は自ずと決まってくる。個人的には同盟国・同志国と、強みを持つ分野を補い合って、エコシステムを形成できればいいと思う。日本は半導体そのもので後れをとっていても、半導体製造の前工程や後工程の製造装置で圧倒的なシェアを持つ企業がある。現実として日本の存在抜きにしてエコシステムが回ることはないはずだ」
「(23年5月に開催された)G7広島サミットの前に、当時の岸田文雄総理とオープンAIのサム・アルトマンCEOが直接会って話をした。この時に交わした日本国内に研究拠点を新設するとの約束をアルトマン氏は果たしてくれた。グーグルも日本に研究拠点を構えている。結果的に生成AIの日本語処理能力は飛躍的に高まることとなった。こうした成果は、他の言語にも応用できる。その意味で、日本は英語圏以外の生成AIとの『結節点』の役割を担うポテンシャルを持っている。グローバルサウス諸国や途上国がAIにアクセスする世界を構築するうえで、日本はアクセスポイントとしての役割を果たしていく必要がある」
●「トップラインを伸ばす」発想
──AIやWeb3、ステーブルコインに関連する市場を拡大するには、キープレーヤーとなる企業の攻めの姿勢が欠かせません。
「日本でのDXは、省力化やモノづくりの自動化など、コスト側にヒットするものが多かった。それも大事だが、デジタル化でトップラインを伸ばすという発想も重要だ。売上高は数量を単価で掛け合わせたものである。このうち数量は(SNSを通じ情報を世界に発信できる)Web2.0の世界において、プラットフォーマーが提供するサービスを活用して拡大させることができるようになった。単価を引き上げるうえで力を発揮するのが、Web3だ。これまで安価に提供されていた価値があるとすれば、NFT(非代替性トークン)を用いることで、グローバル価格に引き直すことが可能となる。ニセコのスキー場でリフトのファストパスをNFTで販売した事例では、価格が何倍にも跳ね上がった。スモールラグジュアリーな寿司屋の席や、眺めの一番いいレストランの席、歴史ある祭りの特等席など、対象はいくらでもある。コストを2割減らすのと、数量や単価が2倍になるのとでは、生み出すインパクトのレベルが全く異なる」
「観光体験のNFT化などで、プラットフォーマー的な企業が、民間から何社か出てきたら面白い。ふるさと納税がなぜこんなに普及したのかというと、数社のIT事業者が競争をし、UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザー体験)を改善したからだ。NFTの作成ツール自体、すでに進化している。加えて、日本はゲームやコンテンツを豊富に持つ国で、Web3の世界との相性もいい。石破政権の大きなテーマである地方創生を含め、活用策は多岐にわたる」
──生成AIやWeb3の利用の拡大とデータ通信量の増加に対応するため、データセンターを新設する動きが広がっていますが、将来的な電力需要の増加への対処も求められることとなります。
「(送電網と通信インフラを一体整備する)ワット・ビット連携の推進を含め、経済産業省と総務省を中心に政策パッケージが打ち出されることとなるだろう。半導体やデータセンター、クラウドサービス、AIファンデーションモデル、AIアプリケーションはミルフィーユのように層を形成しており、企業の呼びかけで一つにまとまるという類の話ではない。トータルの政策をどう進めていくかが重要となると思う」
──スモールモジュールリアクター(小型原子炉)の活用もあり得ますか?
「ないことはないと思う。ただスモールといっても原子炉だ。規制の観点で大きなイニシャルコストが掛かり、発電できる電力量がわずかならば、ビジネスにはならない。ジグソーパズルで一つ、ピースが足りない場合に、それを埋めるピースになり得る技術だと個人的には考えている。だが国民の理解、立地地域の理解がなければ、なかなか前には進まない」
●政府AIは「フル実装」へ
──米国ではイーロン・マスク氏率いるDOGE(政府効率化省)が職員のリストラに動いています。AIの普及により人間の仕事が奪われるといった懸念を持つ人も少なくありません。
「その心配に関しては、私は全く持っていない。そもそも日本はかなりの人手不足の状態で、更にこれが相当なスピードで深刻化していく。霞が関においても、実員は定員を下回った状況だ。デジタル・ガバメント、ガバメント・クラウドの次は、政府AI、行政支援AIをフル実装するステージとなる。(実員が更に定員を下回る状態になったとしても)仕事が回るようにAIを実装していかなければならない。そういう意味で行政改革の色合いもある。産業界においても人口が減少する社会において、いいものを安く大量販売するという価値観だけでは限界が来る。ダイナミックプライシングを導入したホテルがコロナ禍から完全復活を遂げたように、『いいものを高く売る』姿勢への転換が求められている。1万円のモノやサービスを2万円で売れる社会になれば、国として生産性は飛躍的に向上する」
──「新しい資本主義」を引き継いだ石破政権は、物価高という逆風が政権運営を難しくしている印象が否めません。
「物価と賃金の変化には、どうしても時差が生じる。重要なのは、富を地域経済や働き手に対し、しっかりと還元をすることだ。還元されればみんなが豊かになる。生活者の保護という部分では、デジタル技術でフォローできる面もある。例えば、マイナンバーカードを交通系ICのように活用できる仕組みを構築すれば、訪日外国人観光客向けの料金よりも地域住民の運賃を安く設定することが可能となる。いずれにせよ、政策の議論を丁寧に進めつつ、法案を適切なタイミングで成立させていくことが、日本経済にとっても重要だ」
──新年度はAIの実装という点で、どんな1年になりそうですか?
「社会課題の解決につながるAIの導入事例が相次いで生まれる流れ自体、変化することはないだろう。米国や中国ですでに実装されているAI全自動タクシーに関しては、日本でどのようにフルパッケージで実装できるのか、規制改革担当大臣として課題の解決に立ち向かっていく。再来年にはサービスが開始されるというイメージだ。そして、国民生活を守るという視点とともに、AIの成長戦略を実行するうえでも、サイバー対処能力強化法案の成立は何よりも重要なものだ。サイバーセキュリティーは一番の成長分野である。経産省を通じて国内のサイバーセキュリティー産業を育成しようとする動きもある。スタートアップも次々と誕生するのではないか」
◇平将明(たいら・まさあき)
1967年東京都生まれ、89年早大法卒。サラリーマン生活を経て家業である大田青果市場の仲卸会社に入社し、96年に3代目社長となる。03年に東京青年会議所(JC)理事長。05年に衆院選に出馬し東京4区で初当選。経産政務官兼内閣政務官、内閣府副大臣を経て24年10月発足の第1次石破政権でデジタル大臣に就任。行政改革担当大臣、国家公務員制度担当大臣、サイバー安全保障担当大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革)も務める。第2次石破政権では新たにデジタル行財政改革担当大臣も担う。
(聞き手:日本株報道部長 長田善行)
※インタビューは3月21日に行いました。
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。