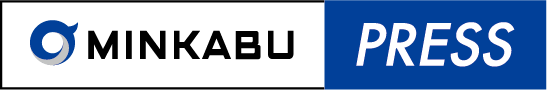8月相場は楽観ムード後退? アノマリーが示すバリュー株の投資妙味 <株探トップ特集>
―日米関税交渉合意でリスクオンに拍車、FRBの姿勢次第でセンチメント急変も―
日米関税交渉の合意を受け、投資家のリスク選好は極まった様相を呈している。米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ期待がくすぶるなか、トランプ政権下の政策に対する楽観論に裏打ちされた「TACO」トレードも横行してきたが、8月は例年、センチメントが変化しやすい時期であり、ジャクソンホール会議を前に楽観一色の地合いが一転するリスクも孕んでいる。こうした不安定な局面に備え、物色の軸足をグロース株からバリュー株へと移す動きが強まることも想定される。
●市場を覆う過剰な楽観とその背景
米国株式市場でS&P500種株価指数、ナスダック総合指数は最高値圏で推移している。CNNの「Fear & Greed Index(恐怖と貪欲指数)」は75超と「Extreme Greed(極めて貪欲)」の水準に達し、暗号資産のビットコインも7月に入り12万ドル台に乗せて最高値を更新した。外為市場ではドル高・円安が進行し、ドル円は1ドル=150円に近づく局面があった。日本株は日米関税交渉の合意が手伝って、東証株価指数(TOPIX)は過去最高値を更新。日経平均株価は一時4万2000円台に乗せ、最高値更新が視界に入った状態だ。
この楽観ムードの背景には、FRBによる利下げ期待も色濃く反映されている。CMEグループ<CME>のFedウォッチツールによると、今月末の米連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ確率は現時点で5%未満にとどまる半面、年内残り3回(9月、10月、12月)のFOMCで都合0.5%以上の利下げが実施されるとの市場コンセンサスは60%超を維持している。
トランプ関税はインフレ要因となるが、6月の米企業物価指数(PPI)は前年同月比2.3%上昇と、5月の2.7%上昇(確報値)や市場予想を下回る結果となった。現時点ではインフレ加速の兆候は見られず、関税引き上げ前の駆け込み需要による在庫調整が功を奏しているものとみられる。ただし、こうした緩衝効果を半年程度とみれば、今秋以降にも関税効果がPPIに顕在化し、来年春ごろに消費者物価指数(CPI)へと波及するとみるのが妥当であろう。
市場はそのようなインフレ加速を一時的なものとみなし、あるいはトランプ政権が「土壇場で妥協した」実績から「Trump Always Chickens Out(トランプはいつも腰が引ける)」との前提でリスク資産に対し強気姿勢を続けてきた。こうした投機的な楽観主義が、上記の英文の頭文字から成る「TACO」トレードに結びつき、過剰なリスク選好地合いを支える方向に作用することとなった。
●8月、センチメント反転の典型的季節性
マーケットが前のめりになる局面は過去にも幾度となく見られたが、こうした地合いは雇用統計やCPIといった米経済指標、あるいはFRBのスタンス転換を契機に一変することが多い。特に8月は、例年センチメントが変わりやすい月として知られる。
注目されるのは8月下旬のジャクソンホール会合である。米カンザスシティー連銀主催のこの年次経済シンポジウムは、FRB議長の講演を通じて市場に大きな影響を与えてきた歴史がある。一昨年となる2023年においては、7月開催分のFOMC議事要旨で利上げリスクが強調され、これを受けてパウエル議長のタカ派姿勢が警戒されることとなり、市場はリスクオフに転じた。24年は波乱こそ小さかったが、7月末の日本銀行の利上げを機に円キャリートレードが巻き戻され、世界的にリスク回避の流れが強まった。
今年はというと、7月のFOMCで利下げ慎重派がそのスタンスを崩さず、更にパウエル議長がトランプ政権に抗する姿勢を再び示した場合、年内の利下げ期待が失望に変わり、楽観一辺倒の市場心理が反転するリスクが高まることとなる。
●今こそ、バリュー株に照準を合わせるとき
センチメントが急変しやすい時期を迎えるにあたり、今のリスク選好が長く続くとの前提に立つのは危ういものがある。仮に米国株を中心としたリスク資産が急落に見舞われれば、日本株もその影響から逃れることはできない。昨年8月や今年4月のような規模の調整に至らずとも、不透明感は依然として横たわっている状況と言えるだろう。
こうした局面でこそ注目したいのがバリュー株である。国内では超長期金利が急騰しており、財政拡大路線への懸念が金利上昇圧力となって表れている。多少後ずれするとしても、日銀の金融政策の正常化に向けた姿勢が続く可能性が高いことを踏まえれば、金利上昇を嫌気するグロース株から、相対的に利上げ耐性のあるバリュー株への資金シフトが起きて当然といえよう。
加えて、株主還元強化の流れも見逃せない。24年には上場企業全体で自社株買い枠として約17兆円が設定され、このうち同年1~5月の間に約9兆円が発表された。今年は5月までにすでに12兆円に達しており、昨年のペースを踏まえると、年間の買い入れ規模は22兆円を超える規模になる公算が大きい。配当総額も26年3月期には20兆円と、5年連続の過去最高更新が視野に入っている。増配や自社株買いは主にバリュー株に見られる傾向であり、資本効率の改善と株主還元の両輪が中長期的なリターンを支える要因となろう。
バリュー株とは企業の本来の価値に比べて株価が割安な状態にある株式のことを指し、割安感を測る具体的な指標として、バリュー株指数はPBR(株価純資産倍率)を基準としている。東証プライム、スタンダード合わせてPBR1倍割れ銘柄は未だ約4割に及ぶ。以下、この先に選好すべき銘柄群を整理したい。
●洋缶HD・ニプロなどに注目
包装容器最大手で圧倒的なシェアを誇る東洋製罐グループホールディングス <5901> [東証P]は自社株買いの真っ最中である。26年2月までに300億円を上限に買い付ける予定であり、6月末時点で約170億円の買い付けを実施した。26年3月期連結最終利益は前期比2.1倍で過去最高を予想している。株価は3000円の大台乗せを果たし、1996年以来の高値圏で推移している。
使い捨て医療器具大手であるニプロ <8086> [東証P]は、大株主の日本電気硝子 <5214> [東証P]と持ち合いの解消を進めていることなどから今年前半の株価は低迷したが、ようやく底を打ち、反転の兆しを見せている。同社は東京CPF(細胞培養施設、東京都羽村市)の底地に関する信託受益権の譲渡契約を締結して固定資産売却益を計上するなど、資本効率の改善に取り組んでいる。中期経営計画では27年度までにROE(自己資本利益率)10%以上を目指すという。業績面では26年3月期の連結経常利益が前期比2.2倍になるとの見通しである。
滋賀地盤のスーパーである平和堂 <8276> [東証P]も自社株買いを推進。今年8月までに上限60億円を買い付ける予定になっており、6月末時点で約45億円を買い付けた。26年2月期連結最終利益は連続最高益更新を予想。3~5月期決算は最終利益が前期比8.1%増で着地した。株価は昨年11月から、ほぼ一本調子で上昇トレンドを続けている。
水産物貿易・加工・買い付けが主力の極洋 <1301> [東証P]は、27年3月期にROIC(投下資本利益率)6%、DOE(株主資本配当率)3.0%を目指しつつ、26年3月期の連結経常利益は前期比15.1%増と6期連続で過去最高益を更新する見通し。今期の年間配当は同20円増の150円に増配する方針としたが、DOEの目標水準を踏まえれば、来期は更なる増配が見込めそうだ。株価は20年以降、多少の上下を交えながら緩やかな上昇を続けている。
配電制御システム大手として船舶・産業用では国内首位の寺崎電気産業 <6637> [東証S]は、好調な造船市況を背景に舶用システム製品の受注が大きく伸びている。25年3月期の連結経常利益は期初に減益予想だったが、現実には前の期比4.8%増で着地した。26年3月期は前期比2.7%減との見通しだが、業界環境が良いだけに期中の上方修正が期待できる。今期配当は43円に増配する方針としているが、配当性向が15%に満たないことを考えると、増配の余地は大きい。株価は4月の急落を経て上昇ピッチを速めている。
軸受けメタル首位の大同メタル工業 <7245> [東証P]は、自動車エンジン用で世界高シェアであると同時に大型船舶用が首位であることから、同社も業界環境の改善で株価は4月以降、追い風が吹いている。25年3月期の連結経常利益は減益予想から一転して増益で着地。26年3月期は前期比2.6%増の70億円に伸びる見通しで、3期連続増益を計画する。今期の年間配当は同6円増の24円に増配する方針。中期経営計画では資本効率の改善策として、27年度の配当性向を35%以上とする目標を掲げ、機動的な自社株買いも検討事項に挙げる。PBRは0.5倍未満であることから、更なる具体的な改善策が急がれると言えよう。
市場は時に静かに、そして突然に転換点を迎える。楽観が極まったその瞬間こそ、冷静な視座と構造的な変化に目を凝らすべき時である。目先の米金融緩和期待や政治的イベントに惑わされず、堅実なファンダメンタルズに支えられた銘柄に軸足を移す姿勢が、いま求められている。ただ、転換点を迎える時期が後ずれすればするほど、負のインパクトが大きくなる点には注意したい。
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。