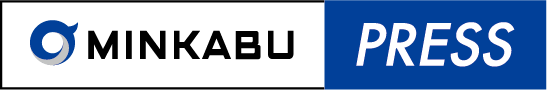AI需要は引き続き拡大、ではこれから何が儲かるのか<今中能夫の米国株ハイテク・ウォーズ>
◆佳境迎える4-6月期決算、TSMC好決算で見えてきたもの
2025年4-6月期決算が始まった。すでに注目企業の決算発表が相次いでいるが、先陣を切って発表された台湾積体電路製造(TSMC)<TSM>が好決算だった。純利益が前年同期比60.7%増の3982億台湾ドル(135億米ドル)と過去最高を更新し、今期の売上高見通しも、従来の20%台半ばの伸びから30%増へと引き上げた。AI(人工知能)半導体向けが好調だが、TSMCの強みはエヌビディア<NVDA>、アドバンスト・マイクロ・デバイシズ<AMD>の汎用AI半導体からブロードコム<AVGO>の特注型AI半導体までの受託生産を一手に引き受けていることだ。1-3月期同様、4-6月期もトランプ関税に対応した駆け込み需要が含まれているだろうから、7-9月期は減速するかもしれないが、このままだと来期も好業績が続くと思われる。
今年になってからAI半導体の需要拡大については、中国発の生成AI「ディープシーク」などの影響もあり、曲がり角を迎えているのではないかと見ていた。実際には、大手ハイテク企業の設備投資動向を見ると、AI半導体の需要は引き続き活発に伸びているようだ。7月24日早朝(日本時間)に発表されたアルファベット<GOOG>の25年4-6月期決算では、設備投資が1-3月期の172億ドルから224億ドルに急増している。同社のクラウドサービス、「グーグルクラウド」向けの設備投資が増加していると思われる。「グーグルクラウド」の業績は好調だが、クラウドサービスの事業規模と比べて設備投資が大きすぎる感じがする。AI半導体の需要動向については、アルファベットだけでなく、これから発表されるマイクロソフト<MSFT>、アマゾン・ドット・コム<AMZN>、メタ・プラットフォームズ<META>等の大手ハイテク企業の設備投資の動向に注目したい。
一方、先日、エヌビディアのジェンスン・フアンCEO(最高経営責任者)が発表した、中国向けAI半導体「H20」の対中輸出規制解除の影響はまだ表れていない。TSMCが「H20」の生産を再開するまでに約9カ月かかるというが、その間にファーウェイが新型AI半導体の量産体制を整備するかもしれない。ただし、株式市場ではエヌビディアやマイクロソフトのような生成AI関連の超大型株に対する評価、期待が依然として高い。それだけにこれら超大型株の決算が注目されるところだ。
他の半導体セクターの有力企業では、ASMLホールディング<ASML>の決算内容やガイダンスが市場の期待に届かず、失望売りを誘った。なぜ、半導体の両雄にこれほどの差が生じたのだろうか。これまで、最先端露光装置を世界で唯一製造する同社の業績は、世界最大の半導体メーカー、TSMCの業績と相関関係があった。ところがここに来て、その構図が崩れ始めている。というのもAI半導体が主流となったいまでは、前工程に属する露光装置に必ずしも最先端技術が求められなくなっているからだ。
また、最新型のHigh-NA EUV(高開口数・極端紫外線)露光装置は1台3億5000万ドル以上と言われるほど高価なものだ。従来型のLow-NA(低開口数) EUV露光装置でも2億ドル前後なので一段と高価になっている。TSMCは、Low-NA型でも最先端半導体を生産できる効率的な生産体制を組みつつあると思われる。High-NA型の本格導入は25年後半から量産開始(ウェハ投入開始)の2ナノ・メートル(nm)が有力視されていたが、直近では、2026年後半量産開始の「A16」(1.6nm)でも導入を見送ったという報道もあり、28年量産開始の「A14」(1.4nm)になる可能性もあるという。メーカーとしてのコスト削減の努力とも言えるだろう。ひたすら最先端技術の露光装置を開発して業績を伸ばしてきたASMLにとっては、若干、風向きが変わってきたのかもしれない。
いずれにせよ、TSMCの決算で改めて見えてきたことは、AI半導体の需要は引き続き拡大しているということだ。同社の受注が増加しているのは、それだけAI半導体の実需があるということだからだ。
◆マグニフィセント・セブンの中で投資格差が拡大
では今後、本格化していく米ハイテク企業の決算はどのように見ていけばいいのだろうか。その前提として、ハイテク主要企業の今年に入ってからの株価パフォーマンスを客観的に比較してみよう。ここにきて、明らかになってきたのは、ハイテク企業の中でも株価のパフォーマンスに格差が開いているということだ。
まずマグニフィセント・セブン(以下、M7)の中では、5年前の2020年7月からエヌビディアの株価は16倍超に上昇している。この間、マイクロソフト、アップル<AAPL>、アルファベットは2倍台、メタは3倍近く、テスラ<TSLA>も3倍台に上昇したが、アマゾンは40%台の上昇に過ぎない。5年間ではエヌビディアの株価上昇が群を抜いていることが分かる。
一方、もう少し足もとの株価動向(25年7月18日時点)を見てみると、年初来のパフォーマンスでは、エヌビディアが25%、マイクロソフトが22%、メタが18%上昇しているのに対して、アマゾンは3%上昇とほぼ横ばい、アルファベットは2%下落、テスラとアップルに至ってはそれぞれ13%下落している。4月の安値からの上昇率を見ても、エヌビディアが80%超、マイクロソフトとメタが40%超、イーロン・マスクが社業に専念すると伝わったテスラは50%近く上昇したのに対し、アマゾンは30%台、アップル、アルファベットの上昇率は20%台以下となっている。M7の中でも、パフォーマンスに格差が出てきているのだ。
結局、生成AIムーブメントの先駆者であるエヌビディアとマイクロソフト、そして生成AIが広告売り上げ増に直結したメタと、今回のAIムーブメントのど真ん中にいる企業が、株式市場の評価を高めていることになる。もちろん、他の企業もAIへの投資を積極的に行っており、成果は出ているが、現時点では投資額の大きさが目立つことになっている。
◆個性が出てきた生成AI、「チャットGPT」はエンタメ性で会員急増
特筆すべきは、足もとで最高値を更新したマイクロソフトの動向だろう。同社も一時はアマゾン、アルファベットと同様に、AIへの設備投資の大きさが懸念材料となっていたが、ここにきて評価を高めているのは、出資先のオープンAIの売上高が好調だからだ。ここ数年のAIブームの源流とも言える同社の生成AI「チャットGPT」は、今年4月に週間アクティブユーザー数が世界で5億人に達し、有料会員も昨年10月の約1100万人から半年で2000万人にまで急増していると言われている。
ご存じの通り、生成AIモデルは各社が開発に力を入れ、競争が激しくなっているが、「チャットGPT」の有料会員が急増しているのは、アドバイザリー機能、平たく言うと"お悩み相談"のニーズが拡大しているためと思われる。仕事に関する質問、相談事だけでなく、例えば医療、健康、教育、資格、職場や家族の人間関係など、多くの利用者が職場では相談できないような個人的な悩みも含めて「チャットGPT」に投げかけている模様だ。そもそもマイクロソフトがオープンAIに出資したのは、生成AIをオフィス・ソフトに組み込んだBtoBのニーズを狙ってのものだと考えられていたが、ふたを開けてみればむしろ、BtoCの個人ニーズに合致していた、ということのようだ。
現在、中国発の生成AI「ディープシーク」やアンソロピックの「クロードAI」、グーグルの「ジェミニ」など、様々な生成AIモデルが使われるようになっているが、ここにきて徐々に明らかになってきたのは、それぞれのモデルに個性が出てきたことだ。例えば「クロードAI」なら論理的な文章作成やプログラミング能力、「ジェミニ」なら動画生成といった具合だ。
そんな中、実際に利用し、チャットの回答を見たことがある人なら納得できると思うが、自然な会話能力という点では、数ある生成AIの中で「チャットGPT」が抜きん出ている。こうしたエンタメ性のある個人向けサービスは、ビジネスモデルとしては強い。業務用ではなかなかお金を払いたがらない個人でも、優れたエンタメになら払うからだ。思うにオープンAIは意識してこうしたニーズに応えようとしたわけではないだろう。独自の大規模言語モデルによる学習と推論を繰り返し、生成AIモデルの性能進化の過程で、自然にこうした製品としての特性が生み出されたのではないだろうか。極めて分かりやすい、生成AIの実需例と言えよう。7月30日に発表されるマイクロソフトの決算は、こうした前提に立って注目したい。
◆より高い投資効果を求めるために重要な"サイズ効果"
M7の動向はともかくとして、個人的により投資妙味を感じるのは、準大手、中堅クラスの企業だ。例えば年初来、株価が2倍化したパランティア・テクノロジーズ<PLTR>や50%超上昇のスポティファイ・テクノロジー<SPOT>、30%超上昇のネットフリックス<NFLX>、クラウドストライク・ホールディングス<CRWD>といった企業だ。
ここに挙げた各社は、現時点での株価の勢いは、M7各社を上回っている。これはある意味、当然のことで、M7各社のような規模になってしまうと、いくら好決算であっても事業の成長率は限られてしまう。100億ドル規模の企業が5億ドル売上高を伸ばしても5%成長に過ぎないが、10億ドル規模の企業が5億ドル売上高を伸ばせば50%成長になる。したがって、超大型時価総額の企業よりも相対的に時価総額が小さい普通の大手企業や準大手・中堅クラスの企業のほうが、好業績になったときに株価は上昇しやすい。「サイズ・エフェクト(効果)」と呼ばれるものだが、今後、米国株投資にあたって、より高いパフォーマンスを目指したいと考えるなら、耳目を集めるビッグテック企業より、こうした成長余力の高い企業を選別していくのが得策だろう。
ネットフリックスはすでに7月17日(現地時間)に25年12月期4-6月期の決算発表を終えたが、7月29日のスポティファイ、8月4日のパランティアは、規模こそビッグテックほど大きくはないが、それぞれの分野で強みを持ち、確固たる地位を築きつつあるハイテク企業だ。各社の事業成長が順調に続いているかを精査したい。
◆業績相場と金融相場が混在、年後半の投資戦略は?
最後に年後半へ向けての投資戦略を考えるうえで、無視することができないアメリカの財政状況を見てみよう。4月のトランプ関税発令以降、世界の株式マーケットは二転三転するトランプ大統領の言動に左右されてきた。背景にはリーマン・ショックからコロナ禍を経て、膨れ上がった巨額の財政赤字を解消しつつ、公約でもある大型減税を実施しなければならないというトランプ政権の事情があるのだが、はたしてこの政権が財政赤字を縮小することができるのか、というのが株式マーケットの大きな懸念材料だった。
ところが7月11日に報じられた米財務省の発表によると、2024年10月から25年6月までの累計で関税収入が初めて1000億ドルを超え、6月の財政収支が270億ドルの黒字となったという。追加関税の停止期限切れを迎える前に、これだけの黒字を生み出しているのだ。各国との関税交渉はこれから佳境を迎えるが、現時点でも懸案だった財政赤字の問題が解消されつつある。このままいけば、公共事業を含めた歳出拡大の余地が高まるかもしれない。
これは、株式マーケットにとっては歓迎すべきことだ。FRB(米連邦準備制度理事会)の利下げを待たずに、政府の財政支出によって通貨供給量が増えていくわけだから当然だろう。問題なのは、岩盤支持層であるMAGA層に本当に恩恵があるのかどうかだ。
7月4日に成立した減税と歳出削減に関する法案「ひとつの大きく美しい法案」は高所得者層と企業に恩恵をもたらすだろう。そして、この減税による財政の悪化は関税収入の大幅増によって最小限度になると思われる。だが、中低所得者層を中心としたMAGA層にとっては、関税収入の大幅増加はいずれアメリカ国内の価格に転嫁されるため大きな負担になる可能性がある。関税はアメリカ企業であれ海外企業のアメリカ子会社であれ、アメリカの輸入業者が払うからだ。いま、MAGA層の中でトランプ政権に対する懐疑の声が上がっているという報道があるが、来年の中間選挙に向け、トランプ大統領がどのように動いていくのかは、引き続き注目すべきだろう。
ともあれ、関税効果で財政赤字が解消されるなら、株式市場にとっては結果オーライだ。4月の株価暴落以降、「TACOトレード」ではないが、こうしたポジティブなサプライズが続くときは、米国の株式マーケットは皆が揃って"イケイケドンドン"となり、懐疑論などかき消されてしまう。それが現在の株高の要因だ。しかし、6月のCPI(米消費者物価指数)のように関税率の上昇によると思われる物価上昇が見えてくると、それを株式市場は心配し始めるかもしれない。
つまり、現在の米国株マーケットは、業績で投資判断が下される業績相場の要素と、カネ余りの金融相場の要素が混在しているということだ。金融相場の様相が強くなれば、モメンタム重視になりがちで、どうしても大型株に資金が集中しやすくなる傾向がある。年後半へ向けての投資戦略を組み立てるためには、そうした一筋縄ではいかない相場の状況を把握しておくことも重要だろう。
米国企業以外では、やはり中国のハイテク企業にも注目すべきだろう。中国の半導体メーカーがスペックの劣る「H20」で高性能のAIをつくれているのだから、恐らくAIの開発能力、データセンターを含むシステムの構築能力ではすでに中国企業がTSMCの主要顧客である米ハイテク大手企業より勝っていると思われるし、株価の面でも伸びしろがあるのではないか。実際、ジェンスン・フアンCEOが「H20」の対中輸出規制緩和を発表した翌日の株価は、エヌビディアが4%上昇に留まっていたのに対して、中国の阿里巴巴集団(アリババ・グループ)<BABA>は8%上昇している。AI相場はまだ続くとしても、こと投資対象として考えるなら、これまでのようにビッグテック一辺倒ではなく、視野を広げて国際分散投資をするのが賢明だということだ。この意見にはやはり変わりがない。
【著者】
今中能夫(いまなか・やすお)
楽天証券経済研究所チーフアナリスト
1961年生まれ。大阪府立大学卒業。岡三証券、シュローダー証券、コメルツ証券などを経て2005年より現職。1998~2001年、日経アナリストランキングソフトウェア部門1位、2000年、同インターネット部門1位。ハイテク業界、半導体業界を対象にした綿密な企業分析に定評がある。楽天証券の投資家向けサイト「トウシル」で注目企業の詳細な決算分析動画およびレポートを随時、公開中。
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。